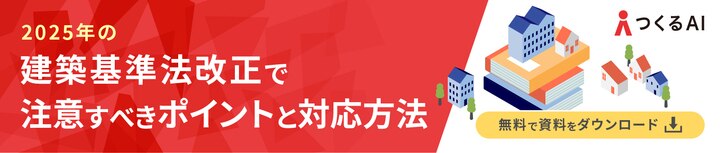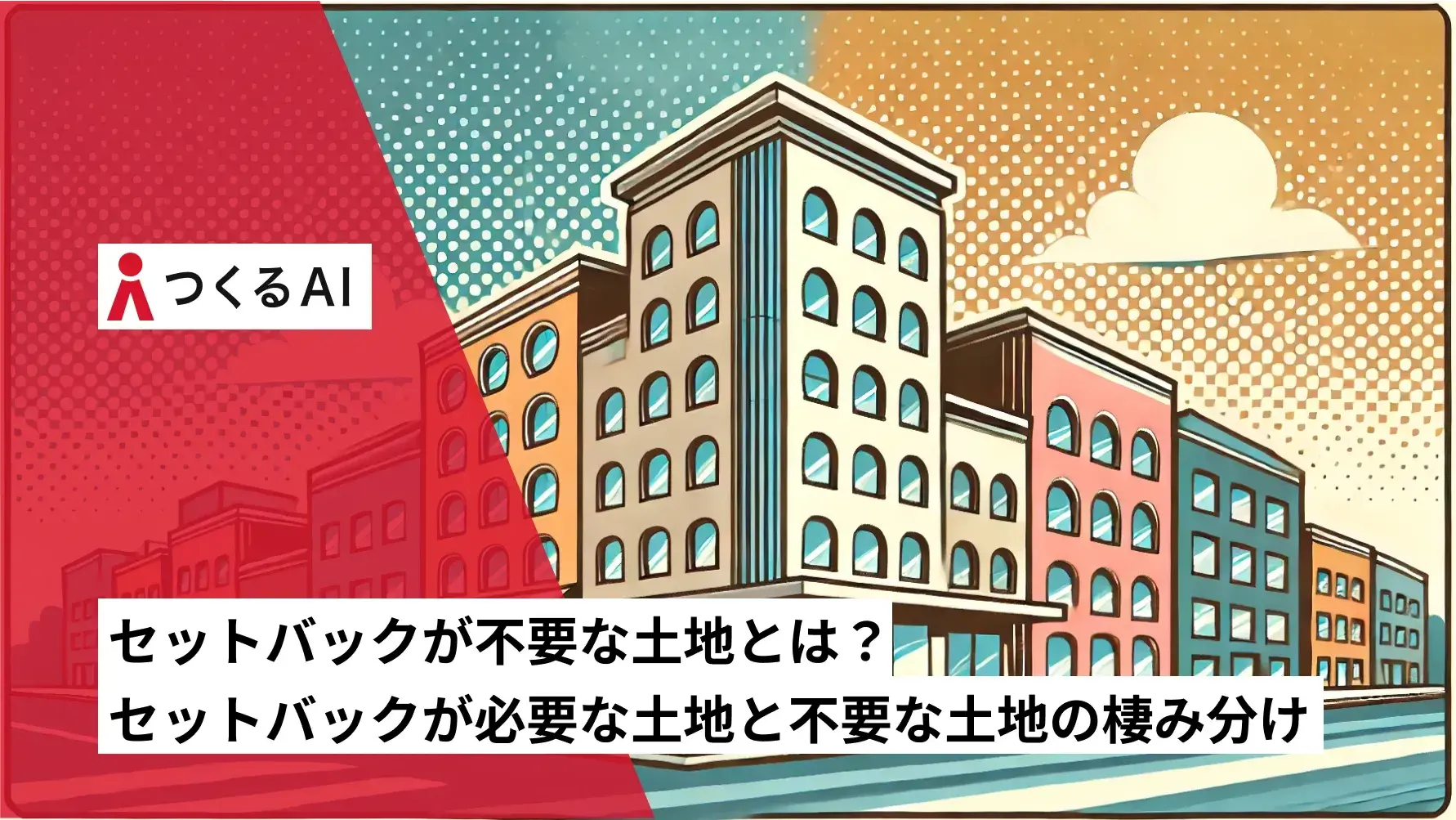
セットバックが不要な土地とは?セットバックが必要な土地と不要な土地の棲み分け
目次[非表示]
◆2025年の建築基準法の改正点を確認!
投資の検討をする際、土地に関するさまざまな要件や規制を確認することが重要ですが、その中でも「セットバック」という単語は重要な概念の一つと言えます。
これは、建物を建築する際に敷地境界線から後退させる規定で、特に道路に接する土地では非常に重要な要素です。
ですが、セットバックの必要な土地要件はいくつかあります。
そのため、投資検討をしている中で、「この土地はセットバックが必要なのか?」と悩む方も多いでしょう。
実際には、セットバックが必要な土地は限られていますが、複雑な規制が絡むこともあり、セットバックの要不要に関しては事前の確認が必要になります。
本記事では、セットバックが必要な土地と不要な土地の違いをわかりやすく解説し、検討している土地がセットバックの対象になるかどうかを見極めるためのポイントをご紹介します。
1.セットバックとは?基本を押さえておこう

セットバックについて簡単におさらいしておきましょう。
セットバックは、主に道路の安全確保や緊急車両(救急車、消防車など)の通行を目的として、建物を道路から一定距離後退させることを言います。
特に、一般的に二項道路ともよく呼ばれる幅員が4m未満の道路沿いでは、道路の中心線から敷地境界線に2m以上の距離を確保する必要があり、この際に強制的にセットバックが必要になるのはよく知られた事例です。
セットバックがさらなる容積消化や斜線をかわすために使われるケースがありますが、そのケースについては別記事で特集していますので下記のリンクをご覧ください。
参考:【3Dでわかりやすく】セットバックとは?どうして道路斜線が緩和されるの?
前述のように、土地の中には二項道路のように、「強制的にセットバックが必要な土地」が存在します。
一見この規制は複雑に見えますが、実はセットバックが必要な土地のパターンの方が少ないのです。
そこで、ここからはセットバックが必要な土地に焦点を当てながら解説していきます。
あなたが情報を持っているその土地がここから記載する条件に当てはまらなければ、セットバックが不要な土地と言えるでしょう。
2.セットバックが必要な土地と不要な土地の棲み分け

セットバックが必要な土地と不要な土地を見分けることは、土地購入や建物の建築計画を進める上で非常に重要です。
セットバックが必要な土地は、特定の条件を満たす場合に限られており、実際には不要なケースの方が多いです。
ここではセットバックが必要か不要かについての見極め方法を解説します。
2.1. セットバックが必要な土地の種類は少ない
まず、セットバックが必要な土地の種類は限られています。
明確にセットバックが必要な土地の典型例として、以下のような土地が挙げられます。
-
二項道路(建築基準法第42条2項に該当する道路)
- 都市計画道路(将来的に拡幅が予定されている道路)・再建築不可の指定区域
これらの道路に面している土地の場合、セットバックが必要です。
しかし、一般的にはそれ以外の道路に面している土地や、既に道路幅が十分に広い土地ではセットバックは不要です。
そのため、このリストに当てはまらない場合、基本的にセットバックは不要です。
2.2. 例外について
ただし、上記の1・2に当てはまっている条件の場合でも、セットバックが不要になるケースがあります。
それは建築基準法42条第三項に該当する道路で、諸般の事情によりセットバックが難しい場合は中心線から1.35m~2mの距離を指定して、その特定の距離が中心線から確保できていればOKと、する事例です。
ですが、この事例は基本的にはごくまれですので、もちろん調査の上で検討を進めるという前提に立ちつつも必ずしも重要視する必要はないと言えます。
また、それ以外にも、各都道府県の条例によって細かくセットバック要件が指定されているケースもあります。
詳細は次のセクションをご覧ください。
また、道路中心線などの概念が分からない方は下記のリンクから参照記事をご覧いただけます。
参考:セットバックの道路中心線ってどう決まるの?測量図に記載されていない時はどうする?
3.セットバックが必要な土地の種類とは?

ここまでは、セットバックが必要となる土地の種類を簡単に解説してきました。
ここからは、それらの条件について、もう少し具体的に掘り下げて説明していきます。
セットバックが義務付けられる土地の多くは、道路や建築基準法に関連した条件を満たすケースがほとんどです。
特に、二項道路や都市計画道路に接する土地は、セットバックの対象となりやすいため、注意が必要です。
3.1. 二項道路のセットバックについて
「二項道路」とは、建築基準法第42条第2項に定められた道路のことを指します。
これは、道路幅員が4m未満の狭い道路で、既存の建物が建てられた当時は合法であったが、現在の基準では道路の幅が不足している道路を指します。
このような道路に面している土地に新しく建物を建てる場合、道路の中心線から2m以上セットバックする必要があります。
セットバックが必要な理由は、道路幅を広げ、将来的に安全な通行を確保するためです。
特に緊急車両(救急車や消防車など)の通行を可能にし、防災や交通の安全性を向上させるために、この規定が設けられています。
3.2. 都市計画道路のセットバックについて
次に「都市計画道路」です。
都市計画道路は、将来的に拡幅が予定されている道路で、都市計画区域内に指定されています。
こうした道路に面している土地では、都市計画に従って、道路の幅が広がることを見越したセットバックが求められることがあります。
都市計画道路のセットバックは、通常の道路よりもさらに厳しい基準が設けられている場合があり、建物の位置や敷地の利用計画に大きな影響を与えることがあります。
そのため、都市計画道路には注意が必要です。
都市計画図に記載されているため、入念に確認し、投資検討時にどれくらい道路に面積を取られてしまうのかを把握しておくとよいでしょう。
3.3. 各都道府県の条例によるセットバック規制
さらに、各都道府県や自治体ごとに、独自のセットバックに関する条例や規制が存在する場合があります。
これらの条例は、地域の特性や都市計画に基づいて設けられており、特定の条件に該当する土地ではセットバックが必要になることがあります。
例えば、東京都建築安全条例では、大規模建築物の接道条件について、延べ面積に応じて接道の長さや幅員を規定しています。
京都府の建築基準法施行条例では、都市計画区域内において、道路の一端が幅員1.8メートル未満の道に接続する場合、その道内や道に突き出しての建築物の建築や通行上支障がある工作物の築造を禁止している例もあります。
また、路地状敷地に関する規制も見られ、東京都建築安全条例では、路地状部分の長さに応じて必要な幅員を定めています。
同様の規制は京都府の条例にも存在しており、路地状部分の長さに応じて2メートルから4メートルの幅員の確保が必要になっています。
このように、避難の安全性確保や良好な市街地環境の形成を目的として、地域の特性に応じて各自治体が独自に定める規制が存在します。
建築計画を立てる際には、該当する地域の条例を確認することが重要になってくるため、本格的な投資判断や設計士によるボリュームチェックの段階では役調を行い、要件を確認することが必要となります。
参考1:東京都建築安全条例
参考2:建築基準法施工条例
4.まとめ:セットバックが必要な土地の見極めポイント
セットバックが必要かどうかを見極める際には、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。
まず、道路幅員を確認することが基本です。幅員が4m未満の道路に面している土地の場合、道路中心線から2m以上のセットバックが必要となる可能性が高いです。
特に、二項道路や私道に面している場合は注意が必要です。
これらの条件に該当する土地は、建物を後退させて建築する必要があるため、敷地の有効面積が減る可能性があります。
次に、本格的な投資検討の際には、自治体の条例や規制を確認することも忘れずに行いましょう。
地域によっては、特定の用途地域や都市計画道路に面している場合に、セットバックが義務付けられるケースがあります。
防災対策や交通の安全性を考慮した規定が存在するため、自治体の役所や不動産会社で都市計画図を確認し、土地が将来の道路拡幅計画の対象になっているかを確認することが重要です。
◆2025年の建築基準法の改正点を確認!