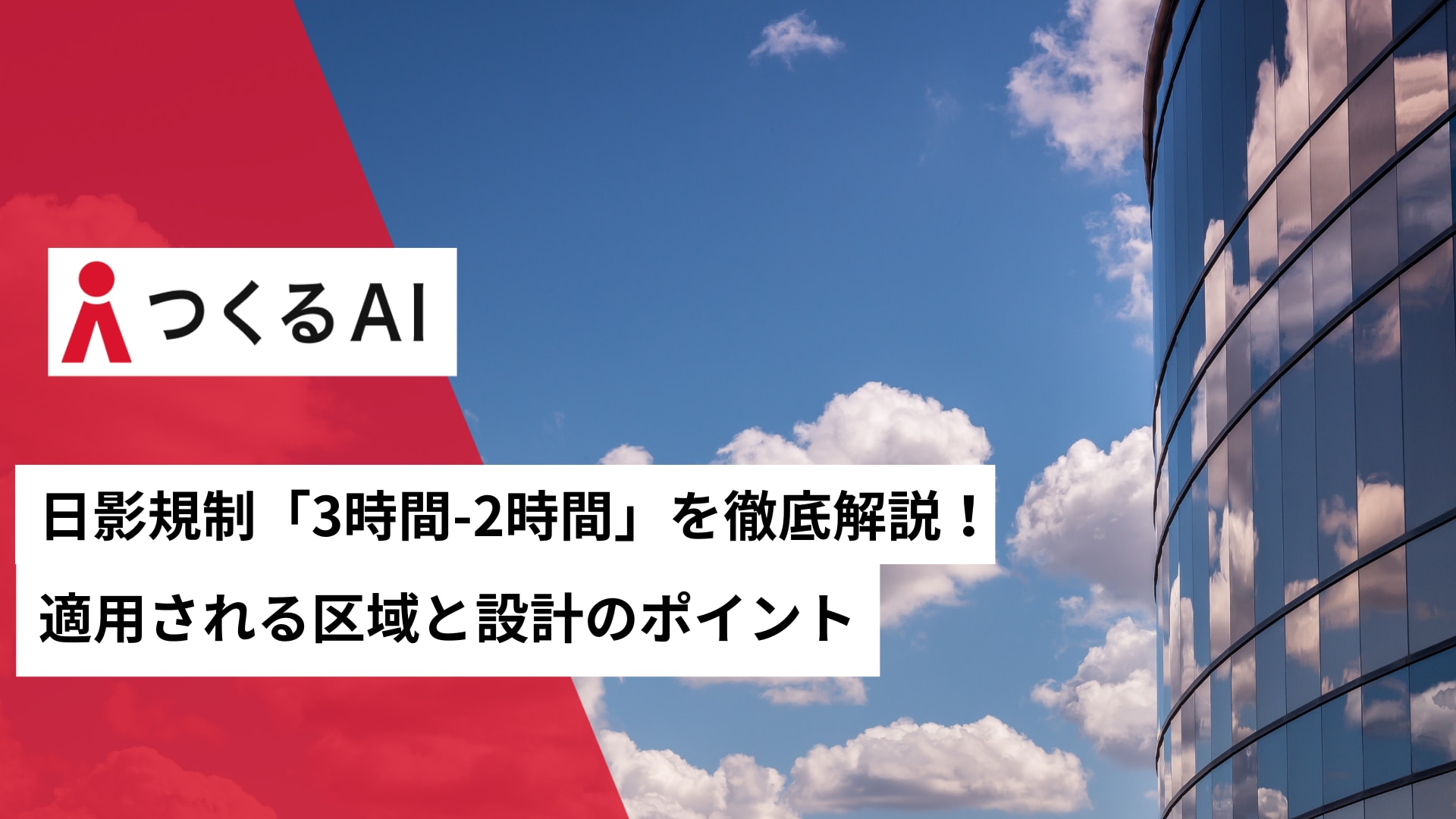
日影規制「3時間-2時間」を徹底解説!適用される区域と設計のポイント
目次[非表示]
建物の高さを左右する日影規制。その内容は、用途地域ごとにいくつかの種類に分かれています。中でも「3時間-2時間」という規制は、比較的規制が緩やかで、中高層の建築物を計画する上で重要な選択肢の一つとなります。
この「3h-2h」とも表記される規制を正しく理解しているかどうかは、土地のポテンシャルを最大限に引き出し、事業性を確保する上で大きな差となって現れます。なぜこの規制が存在し、どのような地域で適用され、そして実務上、どのように対応すればよいのでしょうか。
この記事では、建築・不動産の実務に携わる方々を対象に、日影規制の中でも特に「3時間-2時間」のルールに焦点を当て、その基本的な意味から適用区域、そして規制をクリアするための具体的な設計テクニックまで、専門的かつ分かりやすく解説していきます。
1.日影規制における「3時間-2時間」の基本
まず、「3時間-2時間」という規制が具体的に何を意味するのか、その基本から押さえていきましょう。
1.1. まずは読み解く「3h-2h」の意味とは?
日影規制の「3時間-2時間(3h-2h)」とは、冬至の日において、建物が周辺の土地に落とす影の時間を制限するルールのうちの一種別です。この表記は、測定する場所(測定ラインからの距離)によって、許容される日影時間が異なることを示しています。
具体的には、以下の2段階で規制されています。
- 3時間(3h)の部分: 敷地境界線から5mを超え、10m以内の範囲に適用されます。この範囲では、測定水平面上に建物の影が落ちる時間を「合計3時間まで」に収めなければなりません。
- 2時間(2h)の部分: 敷地境界線から10mを超える範囲に適用されます。この範囲では、同じく測定水平面上に落ちる影の時間を「合計2時間まで」に収める必要があります。
つまり、建物に近い範囲(5m~10m)では少し長く(3時間)、遠い範囲(10m~)ではより短く(2時間)影を落とすことが許容される、という2段階の規制なのです。この関係性を図でイメージすると、より直感的に理解できるでしょう。
1.2. 「3時間-2時間」規制が適用される主な用途地域
この「3時間-2時間」という比較的緩やかな規制は、主に住居系でありながら、ある程度の利便性や建築物の密度が求められる用途地域で採用される傾向にあります。具体的には、地方公共団体が条例で指定しますが、以下のような地域が代表的です。
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
これらの地域は、低層住宅の閑静な環境を厳密に保護するというよりは、中高層のマンションや店舗、事務所などが共存し、都市的な土地利用が図られるエリアです。そのため、「日影規制 3時間 2時間」のルールが、地域の特性に合った規制として選択されることが多くなっています。
1.3. 他の規制時間(例:5h-3h)との違いと位置づけ
日影規制には、「3時間-2時間」の他にもいくつかの種類が存在します。代表的なものに「4時間-2.5時間(4h-2.5h)」や「5時間-3時間(5h-3h)」があります。
- 5h-3h: 5m~10mの範囲で5時間、10mを超える範囲で3時間まで許容。
- 4h-2.5h: 5m~10mの範囲で4時間、10mを超える範囲で2.5時間まで許容。
これらの数値を見比べると明らかなように、「3時間-2時間」は、他の規制に比べて許容される日影時間が最も短い、つまり最も厳しい規制であることがわかります。日照を確保するという観点からは最も保護が厚いルールと言えます。 この規制が適用される地域では、建物の高さや形状に対する制約が大きくなるため、設計にはより高度な工夫が求められることになります。
2.なぜ「3時間-2時間」という規制が設定されるのか
では、なぜ地方公共団体は、数ある選択肢の中から、この最も厳しい「3時間-2時間」という規制を選択するのでしょうか。その背景には、都市計画上の明確な意図があります。
2.1. 高いレベルでの住環境保護の役割
「3時間-2時間」規制が選択される最大の理由は、その地域において特に高いレベルでの日照環境、すなわち良好な住環境を保護・形成しようという強い意図があるからです。日照時間は、住民の快適性や健康に直結する重要な要素です。
特に、中高層の住居が集まる地域において、無秩序に建物が建てられてしまうと、互いの建物の日照を奪い合い、地域全体の住環境が悪化しかねません。そこで、最も厳しい「3時間-2時間」という日影規制を適用することで、新たに建てられる中高層建築物に対して、周辺への日照に最大限配慮することを義務付け、地域全体の居住価値を維持・向上させることを目的としています。
2.2. 中高層建築物に対する明確なメッセージ
この規制は、その地域に中高層建築物を建てるデベロッパーや設計者に対する、行政からの明確なメッセージとも言えます。それは、「この地域では、建物の経済性や収益性だけを追求するのではなく、周辺環境との調和を最優先に考えた計画を立ててください」というメッセージです。
「日影規制 3時間 2時間」が適用されている土地の情報を得た時点で、設計者は、建物の高さやボリュームに大きな制約がかかることを覚悟しなければなりません。そして、その制約の中で、いかにして優れたデザインと事業性を両立させるか、高度な設計力が問われることになります。
2.3. 地方公共団体がこの規制を選択する背景
地方公共団体(特定行政庁)は、建築基準法で定められた範囲内で、地域の実情に応じて日影規制の種類を選択する権限を持っています。その際に考慮されるのは、以下のような点です。
- 地域の将来像(都市計画マスタープラン): その地域を将来的にどのような街にしたいかというビジョン。閑静な住宅街を目指すのか、活気ある商業地を目指すのかによって選択は変わります。
- 既存の街並みとの調和: すでに形成されている建物の高さや密度、住民の生活様式などを考慮し、急激な環境変化が起きないように配慮します。
- 住民の意向: 地域住民が日照環境に対してどのような意識を持っているかも、重要な判断材料となります。
これらの要素を総合的に判断した結果として、特に住環境の質を重視する地域において、「日影規制 3時間 2時間」が選択されるのです。
3.「3時間-2時間」規制をクリアするための建築計画テクニック
最も厳しい「3時間-2時間」規制をクリアし、かつ事業性を確保するためには、高度な建築計画のテクニックが求められます。
3.1. 逆日影計算による建築可能ボリュームの最大化
計画の初期段階で非常に有効なのが「逆日影計算」です。「日影規制 3時間 2時間」という条件を与え、そのルールを守った場合に建てられる建物の最大ボリューム(空間の形)をコンピュータで算出する手法です。
これにより、手探りで設計を始めるのではなく、最初から「建築可能な空間の限界」を正確に把握することができます。この最大ボリュームの中で、必要な床面積や戸数を確保できるか、事業性の見通しを立てることが可能になります。まさに、厳しい規制下での土地ポテンシャルを最大限に引き出すための必須ツールと言えるでしょう。
3.2. 建物の形状と配置の工夫で影をコントロールする
算出された最大ボリュームをヒントに、具体的な建物の形状や配置を工夫していきます。影をコントロールするための代表的な手法は以下の通りです。
- セットバック: 建物の上層階を、下層階よりも内側に後退させる手法です。これにより、高い部分が隣地に落とす影を軽減できます。北側斜線制限への対応と同時に検討されることが多い手法です。
- 雁行(がんこう)配置: 建物の壁面をギザギザに配置する手法です。これにより、壁面が単調な場合に比べて影の落ち方が分散され、特定の場所に長時間影がとどまるのを防ぐ効果が期待できます。
- 建物の高さを北側で下げる: 太陽は南から射すため、建物の北側の高さを低く抑えることで、北側の隣地への日影の影響を直接的に減らすことができます。
これらの手法を敷地形状に合わせて組み合わせることで、「3時間-2時間」の厳しい規制をクリアしていきます。
3.3. 日影シミュレーションによる精密な検証と調整
計画がある程度固まったら、最終的な検証として「日影シミュレーション」を行います。設計した建物の3Dモデルを使い、冬至の日の朝8時から夕方4時まで、時間ごとの影の動きを正確にシミュレートします。
このシミュレーションにより、規制をクリアできているかを最終確認するのはもちろん、あと数センチ建物を削れば規制をクリアできるといった、ミリ単位での精密な調整が可能になります。また、近隣住民への説明会などで、周辺への影響が基準値以下であることを客観的なデータで示すための、信頼性の高い資料としても活用できます。
4.設計実務から学ぶ「3時間-2時間」規制の考え方
最後に、より実務的な観点から、「3時間-2時間」規制とどう向き合うべきか、その考え方を探ります4.1. 準住居地域などでのマンション計画におけるアプローチ
例えば、幹線道路沿いの準住居地域で「日影規制 3時間 2時間」が適用されている土地にマンションを計画する場合を考えてみましょう。この地域は容積率が高く、本来は高さのある建物を建てたいところです。しかし、厳しい日影規制がそれを阻みます。
このような場合、設計者はまず逆日影計算で建てられるボリュームの上限を把握します。その上で、南側は日照を確保するために低層の住戸を配置し、北側や道路側は共用部(廊下や階段)や比較的日照要求の低い部屋を配置するなど、プランニングの工夫で対応します。厳しい規制は、逆に言えば、設計者の創造性を引き出すきっかけにもなり得るのです。
4.2. 緩和規定(道路幅員・角地)を最大限に活用する戦略
厳しい「3時間-2時間」規制下では、わずかな緩和規定も最大限に活用することが重要になります。
- 前面道路の幅員: 敷地の前面道路が広いほど、影の測定開始点が道路の向こう側になるため、規制が有利になります。
- 角地緩和: 2つ以上の道路に接する角地は、2方向から緩和を受けられるため、日影規制上有利な条件となります。
- 高低差: 敷地が道路より高い場合は、緩和を受けられる可能性があります。
これらの緩和規定を全て洗い出し、それらを組み合わせた場合に最も有利になる設計アプローチは何かを戦略的に考えることが、プロジェクトの成功に繋がります。
4.3. 天空率との併用による設計の可能性拡大
天空率の活用も、間接的に「3時間-2時間」規制の攻略を助けます。斜線制限が厳しい敷地で天空率を用いることで、建物の形態に関する自由度が高まります。
例えば、斜線制限に従うと削らなければならなかった建物の部分を、天空率を適用することで建てられるようになったとします。その増えたボリュームを、日影に影響の少ない部分に割り振ったり、逆に日影の原因となる部分を削るための「調整しろ」として使ったりすることができます。日影規制と天空率は直接関係ありませんが、このように複数の規制を複合的に捉え、最適解を探ることが、現代の設計者には求められています。
5.まとめ
日影規制の中でも最も厳しいとされる「3時間-2時間」のルールは、高いレベルの住環境を保護するために設けられた重要な規制です。この規制が適用される地域での建築計画は、高さや形状に大きな制約を受けるため、設計者には高度な知識と技術が要求されます。
しかし、そのルールの意味を正しく理解し、逆日影計算やシミュレーションといった先進技術、そして建物の形状や配置の工夫を駆使することで、規制をクリアしつつ、事業性やデザイン性に優れた建築物を実現することは十分に可能です。
「日影規制 3時間 2時間」は、単なる障壁ではなく、周辺環境と調和した質の高い建築を生み出すための挑戦であると捉え、計画に臨むことが重要と言えるでしょう。









