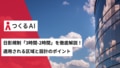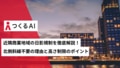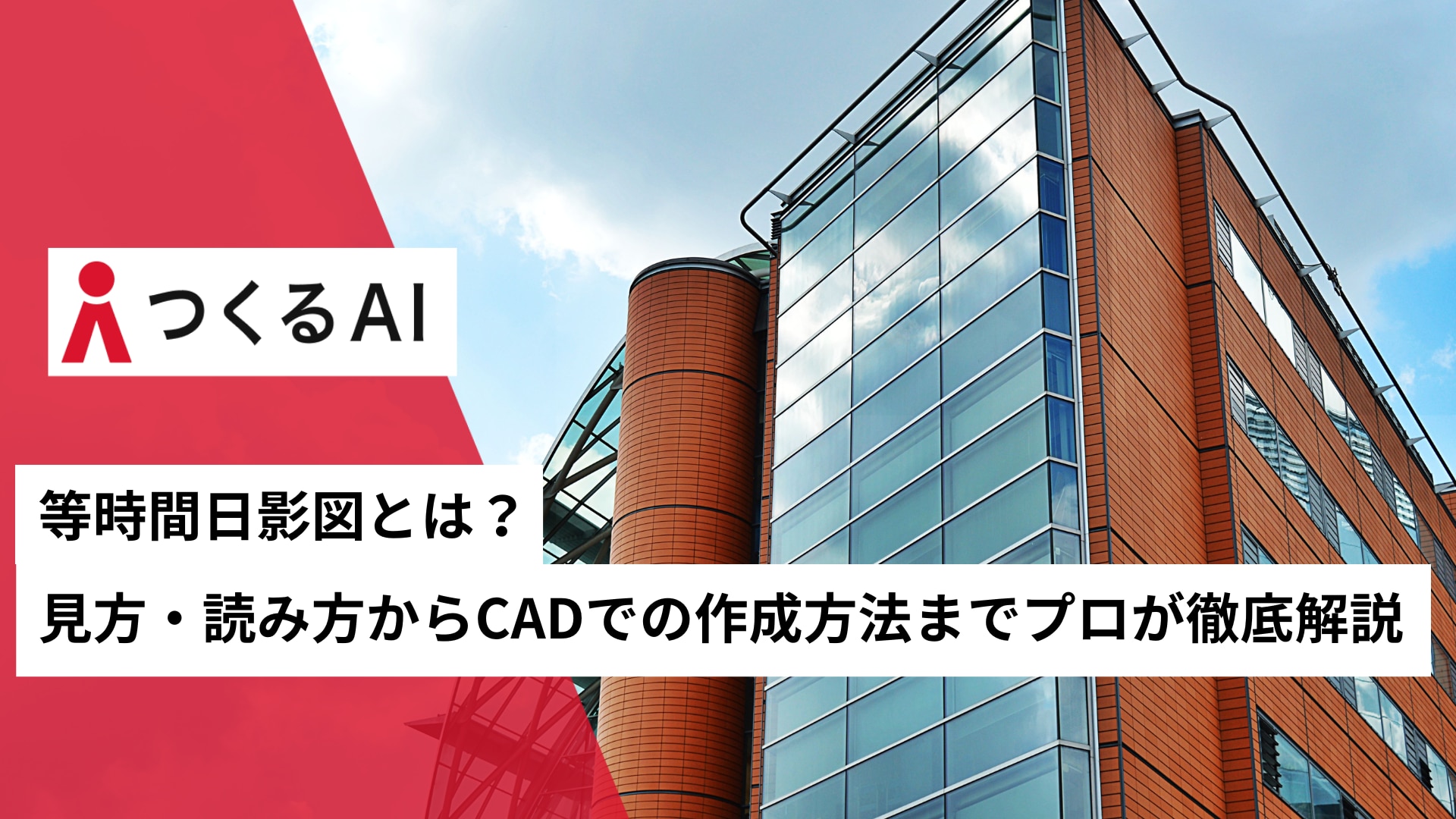
等時間日影図とは?見方・読み方からCADでの作成方法までプロが徹底解説
目次[非表示]
建築設計、特に日影規制が関わるプロジェクトにおいて、必ず目にする図面の一つに「等時間日影図(とうじかんにちえいず)」があります。この一枚の図面は、計画中の建物が日影規制の基準をクリアしているか否かを判断するための、極めて重要な役割を担っています。
しかし、特に経験の浅い設計者や建築を学ぶ学生にとって、等時間日影図の線が何を示しているのか、時刻日影図と何が違うのか、正確に理解するのは簡単ではないかもしれません。
この記事では、建築・不動産の実務に携わるすべての方に向けて、日影規制の検討に不可欠な「等時間日影図」について、その基本的な定義から、具体的な見方・読み方、CADソフトを使った作成方法、そして実務での戦略的な活用法までを、専門的かつ分かりやすく徹底解説します。
1.等時間日影図の基本を理解する
まず、等時間日影図がどのような図面で、何のために存在するのか、その基本的な概念から確認していきましょう。
1.1. 等時間日影図とは?―日影規制をクリアするための「影の地図」
等時間日影図とは、計画中の建物が冬至の日(朝8時から夕方4時まで)の間に、周辺の土地に落とす影の状況を示した図面の一種です。具体的には、「合計で同じ時間だけ日影になる範囲」を滑らかな線で結んで表現します。
例えば、「4時間」と書かれた線の上は、一日を通じて合計4時間だけ建物の影になる地点を結んだ線です。そのため、この線は「等時間線」や「日影等時間線」と呼ばれます。まるで地図の等高線のように、影の時間の長さを可視化したものが等時間日影図なのです。この「影の地図」を使うことで、どの範囲が何時間日影になるのかを一目で把握できます。
1.2. 何のために作成するのか?日影規制への適合性チェック
等時間日影図を作成する最大の目的は、計画している建物が建築基準法で定められた「日影規制」に適合しているかを、客観的に確認・証明することです。
日影規制では、「敷地境界線から特定の距離にある範囲には、〇時間以上の日影を生じさせてはならない」というルールが定められています。例えば、「10mラインの外側は、日影時間が4時間を超えてはならない」といった規制です。
等時間日影図を作成し、規制で定められた「4時間」の等時間線が、規制ラインである「10mライン」を越えていないことを図面上で示すことで、日影規制をクリアしていると判断されます。この図面は、建築確認申請の際に、行政へ提出が求められる重要な書類の一つです。
1.3. 「時刻日影図」との決定的な違いとは?
日影を検討する図面には、等時間日影図の他に「時刻日影図」があります。この二つはよく混同されがちですが、その目的と内容は全く異なります。
- 時刻日影図(じこくにちえいず): 特定の「時刻」における建物の影の形を示す図面です。例えば、冬至の日の午前10時時点での影の形、正午時点での影の形、といった具合に、スナップショットのように瞬間的な影の形状を描きます。複数の時刻の影を重ねて描くことで、影が時間と共にどう移動していくかを確認できます。
- 等時間日影図(とうじかんにちえいず): 特定の「時間」の日影の合計範囲を示す図面です。一日(8時~16時)の影の動きをすべて重ね合わせ、「合計で〇時間影になった範囲」を割り出して線で結びます。例えるなら、長時間露光写真のように、一日の影の軌跡を一枚の図に焼き付けたものです。
時刻日影図が「影の動き」を把握するために使われるのに対し、等時間日影図は日影規制への適合性を判断するための「最終的な結果」を示す図面である、と理解すると分かりやすいでしょう。
2.【保存版】等時間日影図の見方・読み方をマスターする
ここでは、実際の図面を読み解くために必要な、等時間日影図の具体的な見方・読み方のポイントを解説します。
2.1. 最も重要!「等時間線」が示す意味
等時間日影図で最も重要な要素が、曲線で描かれた「等時間線」です。この線には通常、「2h」「4h」といったように、時間が書き添えられています。
例えば、「4h」と書かれた線は「日影等時間線(4.0H)」などと表記され、この線上にある全ての地点が、冬至の日の8時から16時の間に、建物の影になる時間の合計がちょうど4時間であることを示しています。そして、この線の内側(建物側)は日影時間が4時間より長く、外側は4時間より短い、ということを意味します。この線の意味を理解することが、等時間日影図の読み方の第一歩です。
2.2. 日影規制の「規制ライン」とのかかわり
図面上には、等時間線と合わせて「規制ライン」が描かれます。これは、日影規制が適用される範囲を示す線で、通常は敷地境界線から5mや10m離れた位置に破線などで描かれます。
図面を読む際は、この規制ラインと等時間線の位置関係に注目します。例えば、ある地域の規制が「10mラインの外側は、日影時間が4時間を超えてはならない」というものだったとします。この場合、
- OKな例: 「4時間」の等時間線が、すべて「10m」の規制ラインの内側(建物側)に収まっている。
- NGな例: 「4時間」の等時間線の一部が、「10m」の規制ラインを越えて外側にはみ出してしまっている。
このNGな状態は、日影規制に違反していることを意味し、建物の形状を見直す必要があります。等時間日影図の見方とは、この関係性を正しく判断することに他なりません。
2.3. 影を測定する高さ「測定水平面」の読み取り方
等時間日影図の図面情報の中には、必ず「測定水平面の高さ」が明記されています。これは、どの高さの面に落ちる影を計算したかを示す、非常に重要な情報です。
例えば、「測定面高 G.L.+4.0m」や「A.P.+〇〇m」といった表記がされます。G.L.は設計地盤面(Ground Level)、A.P.は東京湾平均海面を基準とした絶対的な高さ(Arakawa Peil)を指します。日影規制では、用途地域によって測定面の高さが1.5m、4m、6.5mなどと定められているため、その規制に合った正しい高さで計算されているかを確認する必要があります。この測定面の高さが変われば、当然、等時間線の形状も大きく変わってきます。
3.等時間日影図の作成プロセスと現代のツール
かつては手作業で作成されていた等時間日影図ですが、現代ではどのように作成されているのでしょうか。
3.1. 作成に必須となるパラメータ(緯度、真北、建物情報など)
等時間日影図を正確に作成するためには、いくつかの重要なパラメータ(設定値)が必要です。これらが一つでも間違っていると、全く意味のない図面になってしまいます。
- 敷地の緯度・経度: 太陽の軌道は緯度によって異なるため、正確な敷地位置の情報が不可欠です。
- 真北の角度: 太陽の動きは真北を基準とするため、敷地に対して真北がどの方向かを示す正確な角度が必要です。方位磁石が示す磁北とは異なるため注意が必要です。
- 建物の3D情報: 計画中の建物の正確な高さ、形状、配置に関する3次元データが必要です。
- 測定水平面の高さ: 適用される日影規制に基づいた、正しい測定面の高さを設定します。
- 計算の時刻範囲: 原則として、冬至の日の午前8時から午後4時までの8時間で計算します。
3.2. 主流はCAD/BIMソフトによる自動生成
現代の建築設計において、等時間日影図の作成は、CADやBIMソフトを使って自動生成するのが一般的です。AutoCAD、Revit、ARCHICADといった主要なソフトウェアには、日影計算機能が標準で搭載されています。
設計者は、前述のパラメータを正確に入力し、建物の3Dモデルを作成すれば、ソフトウェアが複雑な計算を自動で行い、等時間日影図を出力してくれます。これにより、かつては多大な時間と労力を要した作図作業が、短時間で正確に行えるようになりました。この技術革新は、設計の効率化と品質向上に大きく貢献しています。
3.3. 原理の理解に役立つ「日影チャート」による作図
CADが主流となる前は、「日影チャート」と呼ばれる専用の図盤を用いた手書きによる作図が一般的でした。日影チャートは、透明なシートに時刻ごとの太陽の軌跡が描かれたもので、これを建物の立面図や平面図に重ね合わせ、時刻ごとの影の位置をプロットしていくことで、等時間日影図を作成していました。
非常に手間のかかる作業ですが、このプロセスを経験することで、太陽の動きと影の関係や、等時間日影図が描かれる原理を体感的に理解することができます。CADによる自動生成が当たり前になった今でも、この作図原理を理解しておくことは、設計者にとって無駄にはなりません。
4.設計実務における等時間日影図の活用法と注意点
等時間日影図は、単なる確認申請用の図面ではありません。設計プロセスにおいて戦略的に活用することで、その価値はさらに高まります。
4.1. 計画初期のボリュームスタディで活用する
設計の初期段階で、大まかな建物のボリューム(塊)に対して等時間日影図を作成することで、そのボリュームが日影規制に対してどの程度余裕があるのか、あるいは厳しいのかを判断できます。これを「ボリュームスタディ」と呼びます。
もし規制をオーバーしてしまうようであれば、建物の高さを抑えたり、北側の形状を削ったりといった、早い段階での軌道修正が可能です。これにより、設計が詳細に進んだ後での大幅な手戻りを防ぐことができます。
4.2. 設計案の比較検討と最適化を助けるツールとして
例えば、建物の配置や形状についてA案とB案で迷っている場合、それぞれの案で等時間日影図を作成し、比較検討することができます。
- A案は日影規制はクリアできるが、余裕が少ない。
- B案は規制に対して余裕があり、将来の増築などにも対応できそうだ。
このように、等時間日影図を比較することで、日照環境への影響という観点から、どちらの案がより優れているかを客観的に評価し、設計の最適化を図ることができます。
4.3. 近隣説明会での円滑なコミュニケーションのために
中高層の建築物を建てる際には、近隣住民への説明会が開催されることが多くあります。その際、専門的で難解な日影規制の内容を口頭だけで説明しても、なかなか理解を得るのは難しいものです。
そこで等時間日影図が役立ちます。この図面を見せながら、「この線が4時間影になる範囲を示しており、法律で定められたこのラインを越えないように設計しています」と説明することで、視覚的かつ客観的に、法規を遵守し、周辺環境へ配慮していることを示すことができます。これは、住民の不安を和らげ、円滑な合意形成を促すための重要なコミュニケーションツールとなります。
4.4. 作成時に陥りやすいミスと確認のポイント
CADで自動生成できるとはいえ、入力ミスや設定ミスがあれば誤った図面が出力されてしまいます。特に注意すべきは以下の点です。
- 真北の角度の誤り: 敷地測量図に記載された真北の情報を、正確に入力しているか。
- 測定水平面の高さの設定ミス: 適用される規制と異なる高さで計算していないか。
- 敷地や建物の情報の入力ミス: 敷地境界線や建物の輪郭が、設計図通りに正確に入力されているか。
これらのミスは、確認申請の手続きが滞る原因になるだけでなく、最悪の場合、法律違反の建物を建ててしまうリスクにも繋がります。必ず複数人でダブルチェックを行うなど、厳重な確認体制が求められます。
5.まとめ
等時間日影図は、日影規制という複雑なルールを、一枚の図面で明快に可視化する、建築設計における非常に優れたツールです。その見方・読み方を正しくマスターすることは、法規を遵守した安全な建物を建てるための第一歩です。
さらに、現代ではCAD/BIMの活用により、この図面を設計の初期段階から戦略的に利用することが可能になりました。ボリュームの検討、複数案の比較、そして近隣住民とのコミュニケーションツールとして活用することで、等時間日影図は単なる「申請図面」から、より良い建築と社会環境を創造するための「思考ツール」へと進化します。
本記事が、皆様の実務において、等時間日影図への理解を深め、より効果的に活用するための一助となれば幸いです。