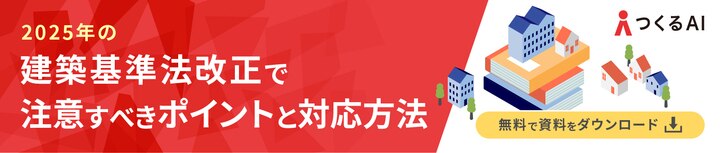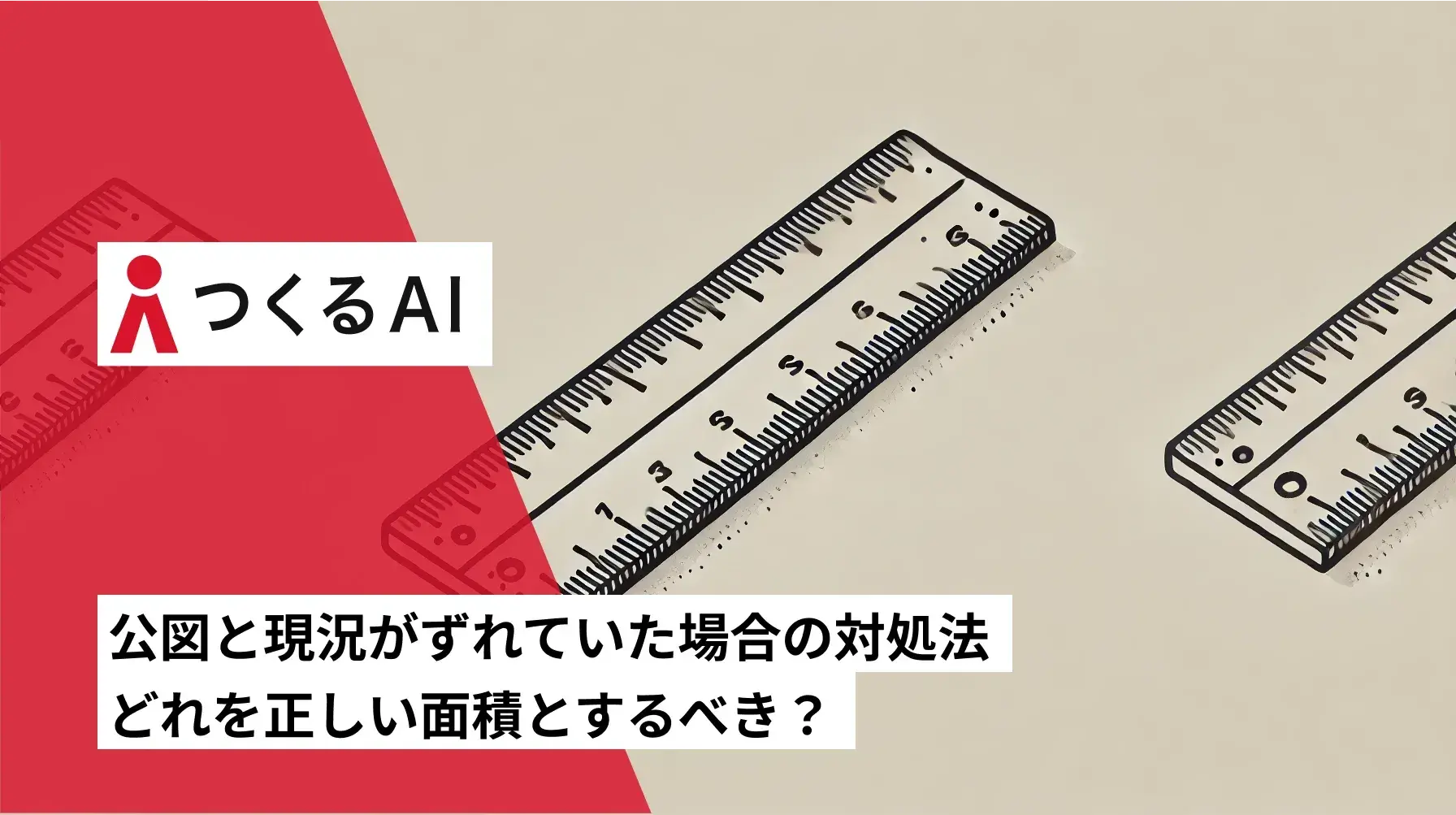
公図と現況がズレていた場合の対処法:どれを正しい面積とするべき?
目次[非表示]
◆建築基準法の改正点を確認!
土地取引や不動産開発の現場では、土地の面積や形状を確認するために「公図」が使われます。
しかし、公図と実際の現地の状況が一致しないケースも少なくありません。
このような「ズレ」が発生した場合、どちらの情報を優先するべきか、土地の正確な面積をどう判断するかは、不動産を扱う上で迷いやすい部分と言えます。
本記事では、公図と現況のズレに関する基本的な知識や、正しい地積を判断するための手順について詳しく解説していきます。
1.公図とは?基本的な定義と役割

公図は、不動産登記法に基づいて作成された土地の図面で、法務局に保管されています。
これは、土地の境界や面積を示す重要な資料であり、不動産取引や土地開発においても基礎的な情報となります。
公図には土地の地番や筆界、さらには土地の形状や位置が記載されています。
法的な役割としては、土地の所有権や取引において基本的な情報を提供するものです。
1.1. 公図の定義と法的な役割
公図は、明治時代の地租改正時に作成された地図が基になっています。
そのため、地域によっては公図の精度にバラつきが見られることがあります。
特に、都市部の一部や古くから存在する区画では、公図に記載された土地の形状や境界線が現況と一致しないケースが見受けられます。
1.2. 公図の作成方法とその精度
公図は、地籍調査や測量によって作成されますが、当時の技術や調査方法に依存していたため、地域ごとに精度の差が生じています。
特に、古い登記や台帳を基にしている公図では、正確さに欠ける場合があるため、現地での状況確認や測量士による再調査が必要になることもあります。
この歴史的背景については次のセクションでご説明します。
2.公図の歴史的背景と法的位置づけ

2.1. 明治時代からの公図の成り立ち
公図の歴史は明治時代にさかのぼります。
1873年の地租改正事業を契機に、全国的な土地の測量と地図作成が行われました。
この時期に作成された改祖図や地押調査図が、現在の公図の原型となっています。
当時、明治政府は全国に測量の専門家を派遣する余裕がなく、地方の役人や村人が地図作成を担当しました。
そのため、初期の公図は精度が低く、現在の地図とは大きく異なる場合があります。
2.2. 公図の法的位置づけ
法的には、公図は不動産登記法に基づいて法務局が管理する重要な文書です。
公図は土地の境界や地番を示す公的な地図として、登記や課税の基礎資料となっています。
しかし、その精度や信頼性には課題があり、現在も地籍調査や法14条地図の作成によって、より正確な地図への更新が進められています。
3.公図と現況がずれる原因とは?

土地の取引や開発の過程で、公図に記載された情報と実際の現地の状況が一致しないケースは決して珍しいことではありません。
これにはいくつかの理由があり、歴史的背景や技術の進歩、自然や人為的な要因が関係しています。
このセクションでは、公図と現況のずれがどのようにして発生するのか、その主な原因について詳しく説明します。
3.1. 公図の歴史的背景
公図の多くは、明治時代に作成されたもので、当時の目的は現代のような精密な土地管理ではなく、税金徴収のためのものでした。
これにより、土地の地積や境界が正確に反映されていない場合があります。
特に、地租改正によって導入された公図は、地籍調査や測量が簡易であったため、現況とずれが生じることがありました。
以下のような具体的な問題が当時から続いています。
-
税金を低く抑えるために、実際よりも小さな面積を申告することが多くありました。
これは、地主が税負担を軽減しようとする行動が背景にあります。
- 一方で、小作地では地主がより多くの小作料を得るために、実際より大きな面積を申告することもありました。
このような土地台帳の不正確さが、現代においても公図と現況のズレを引き起こす原因となっています。
公図の縮尺の違いについては下記の記事にて触れておりますので、気になる方はご覧ください。
参考:公図の縮尺はどうなっている?公図によくある縮尺や計算方法とは
3.2. 測量技術の進歩
明治時代に作成された公図は、現在の測量技術と比べて非常に精度が低く、手作業による不正確さが伴っていました。
そのため、当時の公図には、現在のように精密な地積測量図がなく、土地の面積や形状が大まかにしか記載されていませんでした。
しかし、現代ではGPS技術や精密な測量器具の進歩により、土地の距離や境界線が非常に正確に測定できるようになりました。
これにより、古い公図と現代の測量結果との間に明らかなズレが発生することが一般的です。
特に、都市部では土地の細かい変動や区画の変更が頻繁に行われるため、精度の高い地籍調査が重要となりますが、全国的にすべての地域で完了しているわけではありません。
国土交通省も、この問題を改善するために地籍調査を進めていますが、完全な整備にはまだ時間がかかります。
詳しくは下記の国土交通省のサイトをご覧ください。
参考:地籍調査Webサイト
3.3. その他の要因
公図と現況のズレは、歴史的背景や技術の問題だけではなく、自然や人為的な要因も影響しています。
いくつかの例を挙げると、以下の通りです。
-
土地の形状変更
時間が経過することで、土地の形状が変化することがあります。
特に、土地の境界線が曖昧になる場合もあり、長期間の放置による変動が考えられます。
-
自然災害
地震や土砂崩れ、洪水などの自然災害によって、土地の形状や位置が変わることがあります。
これにより、元々の公図と実際の現地の状況が合わなくなることがしばしばあります。 -
人為的な改変
道路の拡張や区画整理、宅地造成などの開発行為によって、土地の形状が変更されることがあります。
これにより、当初の公図との一致が困難になる場合があります。
公図と現況のズレは珍しいことではなく、むしろ一般的な現象です。
そのため、土地家屋調査士などの専門家は、このズレを前提に業務を行っています。
4.公図と境界確定の関係性

4.1. 境界確定における公図の役割とは
公図は土地の境界を示す重要な資料ですが、必ずしも現況と一致するわけではありません。
境界確定の際には、公図だけでなく、現地調査や測量、隣接地所有者との立会いなど、複数の方法を組み合わせて行います。
4.2. 法務局での公図と境界の管理方法について
法務局が管理する公図には、地図(法14条地図)とそれに準ずる図面があります。
法14条地図は高い精度を持ち、境界確定の有力な証拠となります。
一方で、それに準ずる図面は精度が低く、参考資料として扱われます。
境界確定の過程で、公図と現況に大きな差異が見つかった場合、登記所に地積更正や地図訂正の申請を行う必要があります。
この際、土地家屋調査士による実測図の作成が重要な役割を果たします。
4.3. ずれた場合の正しい地積はどれか?
公図と現況にズレが生じている場合、どの情報を優先して正しい地積とするかは大事なポイントと言えます。
土地取引や開発計画においては、誤った面積を基に進めてしまうと、売買において大きな影響があります。
このセクションでは、どちらを優先するべきか、具体的な判断基準を説明します。
一般的に、法務局で管理されている公図は、登記情報として法的に重要な役割を果たしますが、必ずしも現況を正確に反映しているわけではありません。
一方、現況は実際の土地の状況を示すため、実務上は現地の測量結果が重視されることが多いです。
したがって、現況と公図が一致しない場合、通常は現況測量を行い、その結果を元に判断することが推奨されます。
売買取引の際、測量をせずに売買が成立することは一般的にはありません。
公図と現況が異なる場合、法的に境界を確定するためには、現況測量に加えて筆界特定制度を利用することがあります。
これは、土地の隣地所有者と協議しながら、境界線を確認・確定する手続きです。
また、行政や法務局と連携し、法的なトラブルを防ぐためにも、適切な手続きを踏むことが大切です。
5.公図と現況がズレた場合の正しい土地面積の確認方法

公図と現況にズレが発生した場合、正確な土地面積を確認するためには、いくつかの具体的なステップが必要です。
このセクションでは、どのような手順で土地の面積を確定するか、具体的な方法を紹介します。
5.1. 現況測量の実施とその重要性
公図と現況にズレがある場合、まず必要なのは現況測量を実施することです。
これは、土地家屋調査士や専門の測量士が実際に現地に出向き、正確な距離や境界線、地積を確認するための作業です。
この測量結果が、今後の土地取引や開発計画において非常に重要な基礎資料となります。
特に都市部では、開発が進むにつれて区画や土地の形状が変わることがあり、従来の公図では現況に対応できないことも多いです。
こうした状況を正確に把握し、必要に応じて登記の修正手続きを行うためにも、現況測量が不可欠です。
5.2. 境界確定手続きの必要性とそのプロセス
現況測量の結果、隣地との境界が曖昧である場合は、境界確定手続きを行う必要があります。
この手続きでは、隣地所有者と話し合い、土地の境界を確定させることが求められます。
境界確定は、土地の売買や開発を円滑に進めるためにも、非常に重要なステップです。
また、境界確定が済んだ後は、その結果を法務局に提出し、登記内容の修正や更正を行います。
このプロセスを適切に実施することで、公図と現況のズレを解消し、正確な土地面積を確定させることができます。
6. 国による、公図の精度向上と登記制度

公図は不動産登記制度において重要な役割を果たしています。
登記簿に記載された土地情報を視覚的に表現するものとして、公図は不可欠です。
しかし、公図は前述の通りの歴史的背景から、現況とのズレが大きくなっています。
そのため、国も公図の精度向上は重要であるという認識を持っており、公図の精度向上に取り組んでいます。
ここでは、登記情報と公図の関わり、その精度向上についてご説明します。
6.1. 公図と登記制度の関係について
登記手続きにおいては土地の分筆や合筆、地積更正が必要な場合があり、その際に公図は参照されます。
また、不動産取引や課税評価にも活用されています。
法務局では、公図デジタル化や閲覧システム整備を進めており、インターネット経由で公図を確認できるサービスも提供しています。
ただし、公図閲覧や写し交付には手数料が必要です。
公図更新や訂正は測量・調査に基づいて行われます。
法務局ではこれらの登記のデータを管理するために法14地図(後述)というものを備え付けておくことが義務付けられています。
6.2. 公図の精度向上について
国は、公図の精度向上を重要視しており、精度向上に取り組んでおり、改善後の地図を「法14条地図」と呼びます。
この法14条地図への切り替えは、不動産情報の管理をより正確にするため積極的に推進されていますが、全国でまだ6割ほどしか公図からの置き換えが終わっておらず、まだ公図から移り変わりが完了するには時間がかかる見込みです。
関連記事:セットバック部分の分筆は必要?寄付か無償使用なのかも含めて解説
参考記事:14条地図作成事業
7.まとめ:公図と現況のずれはどう対処すべきか?
不動産開発や土地取引において、公図と現況がズレることは珍しい問題ではありません。
このずれに対して、正確な現況測量を実施し、境界確定手続きを適切に行うことが、土地の正しい地積を確定するための最も重要な方法です。
公図の法的役割を理解しつつも、現地の状況に応じた判断が必要となるため、測量士や土地家屋調査士などの専門家と協力することが欠かせません。
また、境界の不一致が発生した場合は、行政や隣地所有者との協議を経て、法的な手続きを踏むことでトラブルを未然に防ぐことが可能です。
土地の面積や境界が不明確なままでは取引や開発計画にも支障をきたすため、事前の現況確認が何よりも重要になります。
◆建築基準法の改正点を確認!