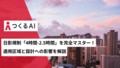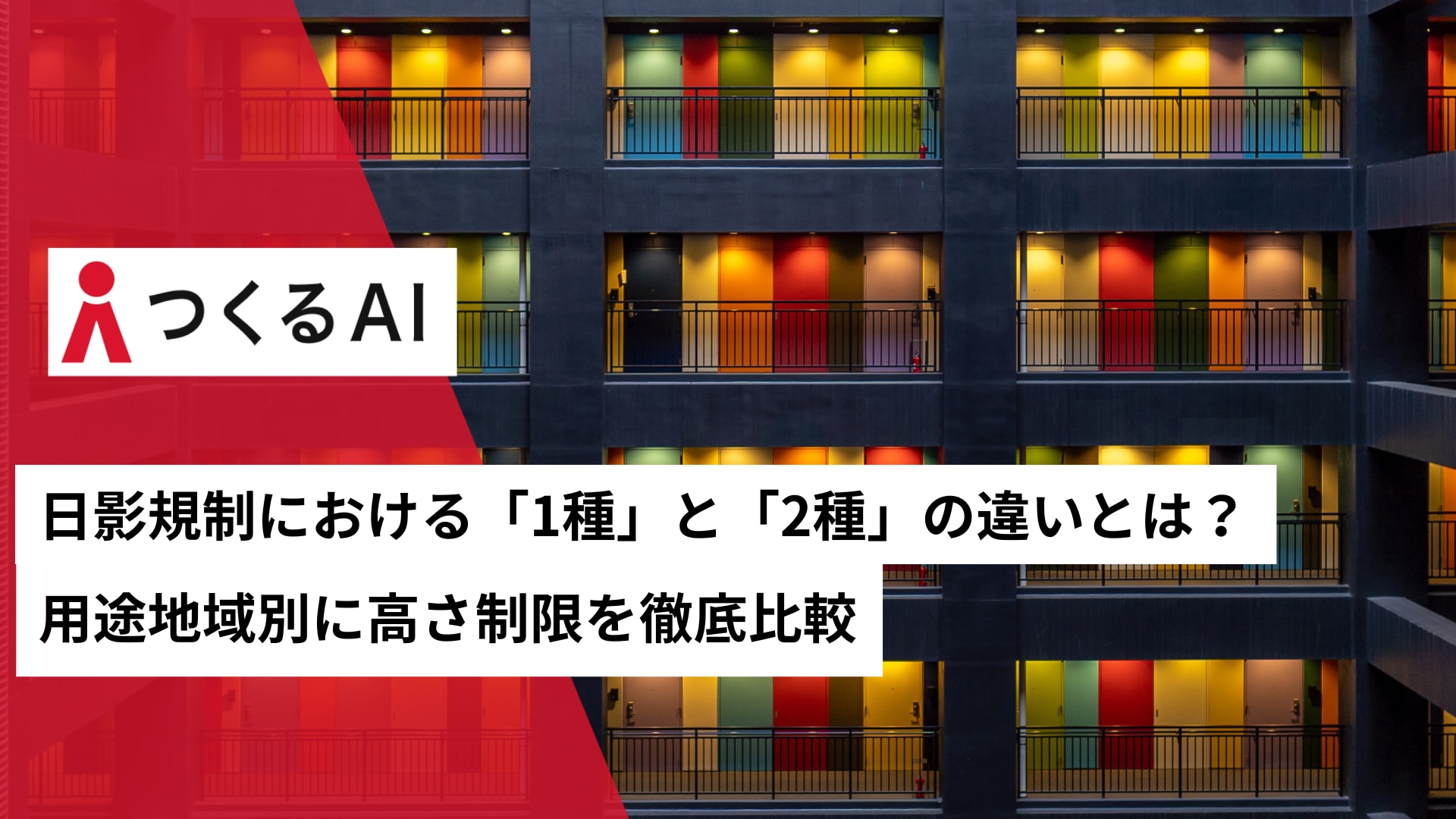
日影規制における「1種」と「2種」の違いとは?用途地域別に高さ制限を徹底比較
目次[非表示]
土地探しや建築計画を進める中で、必ず目にする「第一種低層住居専用地域」や「第二種中高層住居専用地域」といった用途地域の名称。この「第一種(1種)」と「第二種(2種)」というわずかな違いが、実は建築可能な建物の種類や高さ、ひいては日影規制の考え方にまで大きな影響を及ぼすことをご存知でしょうか。
「1種と2種で、日影規制のルールは具体的にどう違うのだろう?」「どちらの土地の方が、より理想に近い建物を建てられるのだろうか?」こうした疑問は、多くの土地オーナー様や設計者の方が抱くものです。
この記事では、日影規制を切り口としながら、用途地域における「1種」と「2種」の根本的な違い、そしてそれが建築計画全体に与える影響について、具体的な規制内容を比較しながら徹底的に解説します。
1.用途地域の「第一種」と「第二種」の基本的な違い
まず、日影規制の具体的な話に入る前に、そもそも用途地域の「第一種」と「第二種」が何を区別しているのか、その基本を理解しておきましょう。
1.1. そもそも「1種」「2種」は何を区別しているのか?
用途地域における「第一種」「第二種」という区分は、その地域でどのような種類の建物を建てることができるかという「用途制限」の厳しさの違いを表しています。非常にシンプルに言えば、以下のように整理できます。
- 第一種(1種): 規制がより厳しく、主に住宅(専用住宅)の良好な環境を守ることを目的としたエリア。
- 第二種(2種): 1種に比べて規制がやや緩和されており、住宅に加えて小規模な店舗や利便施設なども建築可能なエリア。
この基本的な考え方は、「低層住居専用地域」でも「中高層住居専用地域」でも同じです。つまり、「2種」は「1種」の用途制限を少しだけ緩和し、利便性を少しだけ高めた地域である、と捉えることができます。
1.2. 住環境の保護レベルで異なる建築物の用途制限
「1種」と「2種」の最も本質的な違いは、この建てられる建物の種類(用途)の差にあります。
例えば、第一種低層住居専用地域では、建てられるのは基本的に住宅や小中学校、診療所などに限定されます。一方で、第二種低層住居専用地域になると、それに加えて、床面積150㎡までの小規模な店舗(コンビニなど)や飲食店も建てることが可能になります。
この用途制限の違いが、地域の雰囲気や利便性を決定づけます。「1種」はより閑静な住宅街に、「2種」は住宅街の中に少しだけお店があるような街並みになります。そしてこの違いは、日影規制と密接に関わる他の高さ制限にも影響を与えていくのです。
2.【第一種・第二種低層住居専用地域】における規制の違い
ここでは、最も厳しい規制が課される低層住居専用地域に焦点を当て、「1種」と「2種」の違いを見ていきましょう。
2.1. 日影規制のルールは1種・2種で基本的に同じ
まず結論から言うと、日影規制のルールそのものについては、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域とで、大きな違いはありません。
どちらの地域も、日照保護の必要性が非常に高いエリアと位置づけられており、日影規制は最も厳しいレベルで適用されるのが一般的です。具体的には、以下のようなルールが適用されます。
対象建築物: 軒の高さが7mを超える、または地階を除く階数が3以上の建築物。
測定水平面: 平均地盤面から1.5mの高さ。(1階の窓の中心あたりを想定)
このように、日影規制 1種と2種の比較において、規制の計算ルール自体に差は設けられていないことがほとんどです。
2.2. 決定的な違いは「絶対高さ制限」と「用途制限」
では、何が違うのか。低層住居専用地域における1種と2種の決定的な違いは、「絶対高さ制限」と前述の「用途制限」にあります。
絶対高さ制限: この地域では、建物の高さの上限が10mまたは12mに定められています。都市計画によってどちらかが指定されますが、この絶対的な高さの壁があるため、そもそも日影規制が問題になるほどの高層建築物は建てられません。
用途制限: 前述の通り、2種では小規模な店舗が建築可能になります。これにより、住宅以外の建物が建つ可能性が生まれ、地域の景観や利便性に違いが生じます。
つまり、低層住居専用地域を比較検討する際は、日影規制のルールの違いを気にするよりも、「絶対高さが10mか12mか」「店舗などが建てられる2種か、建てられない1種か」という点に注目することが、はるかに重要なのです。
3.【第一種・第二種中高層住居専用地域】における規制の違い
次に、マンションなどが多く建てられる中高層住居専用地域における「1種」と「2種」の違いを見ていきましょう。
3.1. 日影規制の考え方と適用ルール
中高層住居専用地域においても、日影規制の基本的な考え方やルールは、1種と2種で大きくは変わりません。どちらも中高層の共同住宅の良好な住環境を守るための規制です。
- 対象建築物: 高さが10mを超える建築物。
- 測定水平面: 平均地盤面から4mの高さ(または6.5m)。(マンションの2階や3階の窓を想定)
低層地域と同様に、日影規制 1種と2種の比較で、計算ルールそのものに本質的な差が設けられているわけではありません。しかし、後述する容積率や用途制限の違いが、結果的に日影規制の計画に大きく影響してきます。
3.2. 建築可能な建物の規模・種類(容積率・用途)の違い
中高層住居専用地域における1種と2種の主な違いは、建築できる建物の「規模」と「種類」にあります。
用途制限: 2種では、1種で可能な建物に加えて、床面積500㎡までの店舗や飲食店、事務所などが建築可能になります。より大きな商業施設の立地が認められている点が異なります。
容積率: 一般的に、2種の方が1種よりも高い容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)が設定されている傾向にあります。容積率が高いということは、より大規模で、より階数の高い建物を建てられる可能性があることを意味します。
建物の規模が大きくなれば、当然、周辺に落とす影も大きくなります。そのため、容積率の高い2種の土地で建築計画を行う場合は、1種の土地に比べて、日影規制の検討がよりシビアで重要になってくると言えるでしょう。
4.「1種」と「2種」の違いが建築計画に与える影響
これまでの比較を踏まえ、「1種」と「2種」の違いが実際の土地選びや設計にどう影響するのかを考えてみましょう。
4.1. 土地選びの際に必ず確認すべきポイント
土地を選ぶ際には、単に「1種」か「2種」かという名称だけでなく、その背景にある具体的な規制内容を確認することが不可欠です。
- 低層地域の場合: 「絶対高さは10mか12mか?」「将来、隣にコンビニが建つ可能性はあるか?」といった視点で、1種と2種の違いを吟味する必要があります。閑静な環境を最優先するなら1種、多少の利便性を求めるなら2種、という選択になります。
- 中高層地域の場合: 「容積率は何%か?」「どのような用途の建物が建てられるのか?」を確認します。高い収益性を求めるマンション開発などでは、容積率が高く設定されがちな2種の方が有利な場合がありますが、その分、日影規制や北側斜線制限のクリアが計画の鍵を握ります。
4.2. 設計上の自由度と注意点
設計者にとっては、1種と2種の違いは設計の自由度に直結します。 2種の方が建てられる建物の種類や規模の幅が広がるため、設計の自由度は高いと言えます。しかし、自由度が高いということは、それだけ考慮すべき点が増えるということでもあります。
例えば、2種中高層地域で容積率いっぱいの建物を計画する場合、日影規制と北側斜線制限の両方をクリアするために、建物の形状を北側に向かって階段状にするなどの高度な設計テクニックが求められます。日影規制のルール自体は1種も2種も同じでも、設計の難易度は大きく変わってくるのです。
4.3. 事業計画やライフプランへの影響
最終的に、この「1種」と「2種」の選択は、事業計画やライフプランそのものに影響を与えます。
デベロッパーであれば、2種中高層地域で容積率を最大限活用したマンションを計画することで、高い事業収益を目指すことができます。一方、個人でマイホームを建てる場合は、将来にわたって閑静な住環境が保証されやすい1種低層住居専用地域を選ぶことで、穏やかなライフプランを実現できるかもしれません。どちらが良い・悪いではなく、目的(事業性か、居住環境か)に応じて最適な地域を選択することが重要です。
5.まとめ
日影規制における「1種」と「2種」の違いは、規制の計算ルールそのものではなく、主として建築できる建物の「用途」と「規模」に関する制限の違いに現れます。
低層住居専用地域では、日影規制よりも「絶対高さ制限」と「用途制限」の違いが重要です。
中高層住居専用地域では、「容積率」や「用途制限」の違いが建物の規模に影響し、結果として日影規制の検討の重要度を変えます。
「1種」はより住環境保護に特化し、「2種」は住環境を主としつつも利便性を加味した地域です。この根本的な違いを理解することが、土地の特性を正しく評価し、後悔のない建築計画を進めるための第一歩となります。土地の資料を見る際は、「1種」「2種」の文字の裏にある、これらの深い意味をぜひ読み解いてみてください。