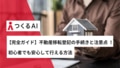【完全ガイド】不動産の個人間売買契約書の作成方法と注意点
目次[非表示]
不動産の個人間売買は、大きな金額が動く重要な取引です。
その中心となるのが売買契約書です。
適切に作成された契約書は、トラブルを防ぎ、スムーズな取引を実現する鍵となります。
本記事では、不動産の個人間売買契約書の作成方法や注意点について、初心者にもわかりやすく解説します。
安全で確実な不動産取引のために、ぜひ最後までお読みください。
1.不動産の個人間売買契約書とは
不動産の個人間売買契約書は、売主と買主の間で交わされる重要な法的文書です。
この契約書には、取引の条件や両者の権利義務が明記されます。
主な記載事項には以下のようなものがあります。
-
物件の詳細情報
-
売買価格
-
決済方法と時期
-
物件の引き渡し時期
-
瑕疵担保責任
- 契約解除の条件
適切に作成された売買契約書は、後々のトラブルを防ぐだけでなく、スムーズな取引の進行を助けます。
2.不動産の個人間売買契約書の作成手順
不動産の個人間売買契約書を作成する際の基本的な手順は以下の通りです。
-
契約書のひな形を入手する
-
物件情報を記入する
-
売買条件を記入する
-
特約事項を追加する
-
両者で内容を確認する
- 署名・捺印する
それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。
2.1. 契約書のひな形を入手する
まず、信頼できる不動産の個人間売買契約書のひな形を入手します。
法務局や不動産関連の団体のウェブサイトで公開されているものを利用するのが安全です。
また、書店で売られている契約書の雛形を購入するのも一つの方法です。
2.2. 物件情報を記入する
次に、売買対象となる不動産の詳細情報を記入します。
以下の項目を漏れなく記載しましょう。
-
物件の所在地
-
土地の面積
-
建物の構造と床面積
- 登記簿上の表示
正確な情報を記入することで、物件の特定を明確にし、後のトラブルを防ぐことができます。
2.3. 売買条件を記入する
売買価格、支払方法、決済日、引き渡し日などの売買条件を具体的に記入します。
特に以下の点に注意しましょう。
-
売買価格:税込みか税抜きかを明記する
-
支払方法:手付金の有無、残金の支払い方法を明確にする
-
決済日:具体的な日付を記入する
- 引き渡し日:決済日と同日か別日かを明記する
2.4. 特約事項を追加する
標準的な契約書の雛形には含まれていない、当事者間で合意した特別な条件がある場合は、特約事項として追加します。
例えば、以下のような事項が考えられます。
-
既存の設備や家具の取り扱い
-
リフォーム工事の実施条件
-
固定資産税の精算方法
- 契約解除の条件
特約事項は、両者の合意内容を明確にし、後のトラブルを防ぐ重要な役割を果たします。
2.5. 両者で内容を確認する
契約書の内容を売主と買主の両者でしっかりと確認します。
不明な点や疑問点があれば、この段階で話し合いを行い、必要に応じて修正を加えます。
2.6. 署名・捺印する
最後に、売主と買主の両者が契約書に署名・捺印します。
通常、契約書は2部作成し、それぞれが1部ずつ保管します。
3.不動産の個人間売買契約書作成時の注意点
不動産の個人間売買契約書を作成する際は、以下の点に特に注意が必要です。
-
物件の正確な表示
売買対象となる不動産の所在地、面積、構造などを正確に記載することが重要です。
登記簿謄本や固定資産税評価証明書などの公的書類を参照し、間違いのないように記入しましょう。
-
売買価格の明確化
売買価格は税込みか税抜きかを明確にし、手付金の有無や残金の支払い方法、支払い期日なども具体的に記載します。
-
瑕疵担保責任の明記
物件に隠れた瑕疵(かし)があった場合の責任について明記することが重要です。
売主の瑕疵担保責任の期間や範囲を具体的に定めておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
-
契約解除条件の設定
契約を解除する場合の条件や手続きについて明確に定めておくことが大切です。
例えば、買主が期日までに残金を支払わない場合や、売主が期日までに所有権移転登記に必要な書類を提出しない場合などの対応を記載します。
-
固定資産税等の精算方法
固定資産税や都市計画税などの公租公課の精算方法について明記します。
通常、売買契約締結時点での未納分は売主が負担し、その後の分は日割り計算で買主が負担するケースが多いです。
- 引き渡し条件の明確化
物件の引き渡し日や引き渡し時の条件(現状有姿か、リフォーム後かなど)を明確に記載します。
また、鍵の引き渡し方法や、設備・備品の取り扱いについても具体的に定めておくと良いでしょう。
4.不動産の個人間売買契約書の記載例
ここでは、不動産の個人間売買契約書の主要な部分の記載例を紹介します。
実際の契約書作成の参考にしてください。
売買契約書
売主 ○○○○(以下「甲」という)と買主 ××××(以下「乙」という)は、
下記物件の売買について次のとおり契約を締結する。第1条(売買物件)
甲は、その所有する下記の不動産(以下「本物件」という)を乙に売り渡し、
乙はこれを買い受けるものとする。記
所在地:東京都○○区××町1-2-3
土地:地目 宅地、地積 100.00㎡
建物:構造 木造2階建、床面積 1階60.00㎡、2階40.00㎡第2条(売買代金)
本物件の売買代金は金3,000万円(消費税込み)とし、
乙は甲に対し、次の通り支払うものとする。手付金:金300万円 本契約締結時
残金:金2,700万円 令和○年○月○日まで第3条(所有権移転時期)
本物件の所有権は、乙が売買代金の全額を甲に支払ったときに、
甲から乙に移転するものとする。第4条(引渡し)
甲は、前条の所有権移転と同時に、本物件を現状有姿のまま乙に引き渡すものとする。(以下、略)
この例は基本的な部分のみを示していますが、実際の契約書ではさらに詳細な条項が必要となります。
5.不動産の個人間売買契約書作成時のよくある質問
Q1. 不動産の個人間売買契約書は自分で作成できますか?
A1. 法的な知識があれば自分で作成することも可能ですが、トラブル防止のため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。
Q2. 契約書の作成に費用はかかりますか?
A2. 専門家に依頼する場合は費用がかかります。
ただし、その費用は後々のトラブル防止や解決のための保険と考えることができます。
Q3. 契約書に記載する売買価格は、実際の取引価格と異なってもいいですか?
A3. 契約書には実際の取引価格を正確に記載するべきです。
虚偽の価格を記載すると、脱税や詐欺などの法的問題につながる可能性があります。
Q4. 契約書の有効期限はありますか?
A4. 一般的に契約書自体に有効期限はありませんが、契約書内に記載された各種期限(決済日、引き渡し日など)は厳守する必要があります。
Q5. 契約書の内容を後から変更することはできますか?
A5. 両者の合意があれば変更は可能です。
その場合、変更内容を記載した覚書を作成し、双方で署名・捺印することが一般的です。
6.まとめ
不動産の個人間売買契約書は、取引を円滑に進め、トラブルを防ぐための重要な文書です。
作成にあたっては、物件情報の正確な記載、売買条件の明確化、瑕疵担保責任の明記など、多くの注意点があります。
初めて不動産の個人間売買を行う方にとっては、契約書の作成は難しく感じるかもしれません。
しかし、本記事で紹介した手順や注意点を参考にすることで、より安全で確実な取引を行うことができるでしょう。
特に重要な取引や複雑な条件がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、より確実に自身の権利を守り、スムーズな取引を実現することができます。
不動産の個人間売買は人生の中でも大きな取引の一つです。
慎重に、そして確実に進めていくことが、将来のトラブル防止につながります。
本記事の情報を参考に、安全で満足のいく不動産取引を実現してください。