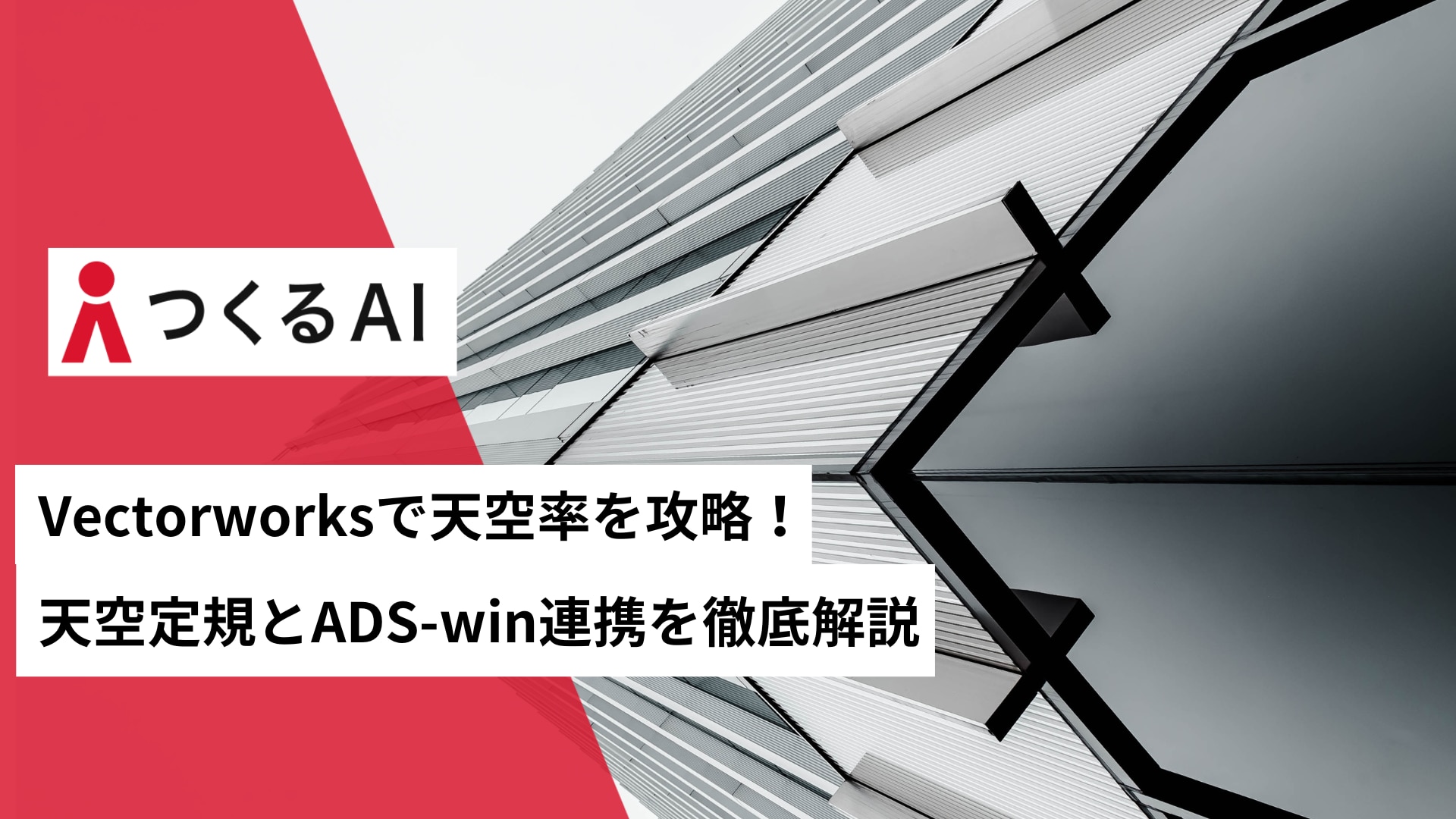
Vectorworksで天空率を攻略!天空定規とADS-win連携を徹底解説
目次[非表示]
1. はじめに:Vectorworksユーザーのための天空率計算ガイド
デザイン性の高い3Dモデリングと、実用的な2D作図機能を両立させたBIM/CADソフトウェアとして、多くの建築士やデザイナーに愛用されている「Vectorworks」。その柔軟な設計環境の中で、避けては通れないのが「天空率」をはじめとする建築法規の検討です。天空率をクリアすることで、斜線制限を超える自由な建築デザインが可能になりますが、その計算は非常に複雑です。
「Vectorworksで設計はしているけれど、天空率の検討は別のソフトや外注に頼っている」という方も少なくないのではないでしょうか。しかし、Vectorworksには、設計ワークフローを止めることなく天空率を検討するための強力な機能が備わっています。
この記事では、Vectorworksユーザーが天空率計算を効率的に行うための具体的な方法を徹底解説します。標準搭載されている「天空定規」ツールの使い方から、デファクトスタンダードである天空率計算ソフト「ADS-win」との連携フローまで、あなたの設計スタイルに合った最適な手法がきっと見つかります。
2. Vectorworksにおける天空率計算の基本アプローチ
まずは、Vectorworksの環境で天空率を検討することが、設計プロセスにどのようなメリットをもたらすのか、そして、どのようなアプローチが存在するのかを整理しておきましょう。
2.1. Vectorworksで天空率を検討するメリットとは?
最大のメリットは、設計と法規検討を同じ環境でシームレスに行える点です。普段使い慣れたVectorworksのインターフェース上で天空率のシミュレーションができるため、思考を中断することなく、デザインの試行錯誤と法規クリアの検証を同時に進めることができます。
ボリュームスタディの段階で建物の形状を少し変更し、すぐに天空率への影響を確認するといったインタラクティブな設計プロセスが可能になります。これにより、設計の初期段階で法規的な裏付けを持つことができ、後工程での大幅な手戻りを防ぎ、プロジェクト全体の生産性を大きく向上させることができるのです。
2.2. 2つの主要な計算方法:「天空定規」と「ADS-win連携」
Vectorworksで天空率を検討するには、大きく分けて2つの方法があります。それぞれに特徴があり、プロジェクトのフェーズや求める精度に応じて使い分けることが重要です。
天空定規ツールの活用: Vectorworks Architectに標準で搭載されている簡易的なチェックツールです。特別な追加投資なしで、設計の初期段階でのおおまかな天空率の当たりを付けるのに非常に役立ちます。スピーディに結果が得られるため、ボリュームスタディに最適です。
「ADS-win」との連携: 天空率計算ソフトのデファクトスタンダードである「ADS-win」(株式会社生活産業研究所)とデータを連携させる方法です。確認申請にも使用できる高精度な計算と帳票作成が可能で、実務における天空率計算の決定版とも言えるワークフローです。
3. 標準機能「天空定規」によるスピーディな検討方法
まずは、Vectorworksに標準搭載されている「天空定規」ツールから見ていきましょう。このツールを使いこなすだけで、設計の初期段階における天空率検討の効率が格段に上がります。
3.1. 「天空定規」ツールの基本機能と設定
「天空定規」は、指定した測定点から見た天空図を簡易的に作成し、計画建築物と適合建築物の天空率を比較表示してくれるツールです。ツールセットから「天空定規」を選択し、ダイアログボックスで敷地境界線や道路幅員、測定点の間隔などを設定するだけで利用できます。
このツールの優れた点は、Vectorworksの3Dモデルを直接参照して、リアルタイムに天空図を生成してくれることです。3Dモデルの形状を変更すれば、その結果が即座に天空定規の表示に反映されるため、非常に直感的な操作が可能です。
3.2. 設計初期段階でのボリュームスタディへの活用法
「天空定規」が最も真価を発揮するのは、設計の初期段階、特に建物の大まかなボリュームや配置を検討するフェーズです。例えば、建物の高さを少し上げてみたり、壁面の位置をずらしてみたりといった操作を行いながら、天空定規の表示を確認することで、「あとどれくらいボリュームを増やせるか」「どこをセットバックすれば天空率がクリアできるか」といった判断をスピーディに行うことができます。このインタラクティブな検討プロセスは、設計の可能性を最大限に引き出す上で強力な武器となります。
3.3. 「天空定規」の限界と実務で利用する際の注意点
手軽で便利な「天空定規」ですが、あくまで簡易的なチェックツールであり、いくつかの限界点も理解しておく必要があります。このツールで生成される天空率は、厳密な三斜求積に基づいたものではないため、確認申請にそのまま利用することはできません。
また、複数の測定点を同時に比較したり、詳細な計算根拠を出力したりする機能もありません。したがって、「天空定規」は設計の初期段階で「当たりを付ける」ためのツールと割り切り、最終的な確認や申請書類の作成には、次に紹介する「ADS-win」との連携を利用するのが、実務における正しい使い方と言えるでしょう。
4. 【推奨】「ADS-win」連携による高精度な天空率計算フロー
設計がある程度固まり、厳密な天空率の検証や確認申請書類の作成が必要になった段階で活躍するのが、天空率計算ソフト「ADS-win」との連携機能です。
4.1. なぜ天空率計算に「ADS-win」との連携が選ばれるのか
「ADS-win」は、多くの審査機関で採用実績のある、信頼性の高い天空率・日影計算ソフトウェアです。その計算結果の正確性と、詳細な帳票出力機能には定評があります。「ADS-win」と連携することで、Vectorworksの持つ優れたモデリング能力と、「ADS-win」の持つ高度な解析能力を両立させることが可能になります。これにより、Vectorworksを設計ワークフローの中心に据えたまま、確認申請まで一気通貫でデータを取り扱うことができるのです。
4.2. Vectorworksから「ADS-win」へのデータ書き出し手順
Vectorworksから「ADS-win」へのデータ連携は、専用のコマンドを実行することで簡単に行えます。基本的なフローは以下の通りです。
レイヤ・クラスの整理: Vectorworks上で、敷地境界線、計画建築物、道路などの各要素を、ADS-winが認識できる所定のレイヤ・クラスに整理します。
データ書き出し: 「ファイル」メニューから「書き出す」を選び、「ADSデータ書き出し」コマンドを実行します。
ADS-winで読み込み: 書き出された専用形式のファイル(.xtf)を、「ADS-win」側で読み込みます。
この簡単な手順で、Vectorworksで作成した3Dモデルの情報を、属性を保ったまま「ADS-win」に渡すことができます。
4.3. 連携で実現するシームレスな設計・解析ワークフロー
この連携機能の最大のメリットは、設計変更への迅速な対応力です。Vectorworks側で建物のデザインを変更した場合、再度データを書き出して「ADS-win」で読み込むだけで、すぐに最新の状態で天空率を再計算できます。モデルの再入力や、2つのソフト間での煩雑なデータのやり取りが不要になるため、設計者はストレスなく設計の修正と検証のサイクルを回すことができます。これにより、より大胆な設計提案と、その法規的な裏付けを、高い次元で両立させることが可能になるのです。
4.4. Vectorworks 2024における連携機能の進化
Vectorworksはバージョンアップのたびに、外部ソフトとの連携機能を強化しています。最新版のVectorworks 2024では、「ADS-win」との連携もさらにスムーズかつ高機能になっています。特に、BIMとして重要な属性情報の受け渡し精度が向上しており、より信頼性の高いデータ連携が実現されています。こうした進化をキャッチアップし、常に最新のワークフローを取り入れていくことが、設計事務所の競争力を維持する上で重要となります。
5. まとめ
本記事では、Vectorworksユーザーが天空率計算を効率的に、そして正確に行うための2つの主要なアプローチ、「天空定規」ツールの活用と、「ADS-win」との連携について詳しく解説しました。
設計の初期段階では、標準機能の**「天空定規」**でスピーディにボリュームスタディを行う。
設計が固まり、厳密な検証や確認申請が必要になったら、「ADS-win」との連携で高精度な計算を行う。
この2つの方法をプロジェクトのフェーズに応じて適切に使い分けることで、Vectorworksの設計環境を離れることなく、天空率という複雑な法規検討をスマートに乗り越えることができます。
使い慣れたVectorworksをハブとして、設計から法規チェックまでを一貫して行うワークフローは、設計の質と生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。ぜひ、本記事を参考に、あなたのVectorworksワークフローに天空率計算を組み込んでみてください。









