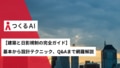【日影規制 対象建築物】あなたの建物は対象?判定基準と高さ・階数の測り方
目次[非表示]
- ・1. 日影規制の第一歩!対象建築物かどうかの判定フロー
- ・1.1. ステップ1:建築地の「用途地域」と「指定の有無」を確認する
- ・1.2. ステップ2:用途地域ごとの「対象建築物」の基準を照合する
- ・1.3. 最終確認:最も重要な地方公共団体の条例をチェックする
- ・2. 【用途地域別】対象建築物の具体的な基準を徹底解説
- ・2.1. 低層住居専用地域:「軒高7m」または「階数3」がボーダーライン
- ・2.2. 中高層住居専用地域など:「高さ10m」が基準
- ・2.3. 商業・工業地域など:条例で指定がある場合のみ「高さ10m」超
- ・2.4. 対象建築物の基準一覧表(まとめ)
- ・3. 高さ・階数の正しい測り方と専門用語
- ・3.1. 「軒の高さ」とはどこを指す?屋根の形状が与える影響
- ・3.2. 「地階」の定義と「階数」の数え方のルール
- ・3.3. 最も重要な「地盤面」の考え方と高低差のある土地
- ・3.4. 意外な落とし穴「工作物」の扱い
- ・4. 日影規制の対象外となるケースとよくある誤解
- ・5. まとめ
「3階建ての家を建てたいけれど、日影規制は大丈夫?」「計画しているアパートは、規制の対象になるのだろうか?」 建物を計画する際、多くの人が最初に直面するのが、この「日影規制」の壁です。しかし、日影規制はすべての建物にかかるわけではありません。法律は、規制の対象となる「日影規制 対象建築物」を明確に定めています。自分の計画がこの対象になるか否かを正確に判断することが、建築計画の第一歩となります。
この記事では、日影規制の核心部分である「対象建築物」にテーマを絞り、どのような建物が規制の対象になるのか、その判定基準と、間違いやすい高さ・階数の測り方を徹底的に解説します。この記事を読めば、ご自身の計画が規制の対象となるかの一次判断ができるようになり、スムーズな計画進行の助けとなるはずです。
1. 日影規制の第一歩!対象建築物かどうかの判定フロー
自分の建物が日影規制 対象建築物に該当するかどうかは、以下の3つのステップで確認していくのが基本です。この流れを理解することで、複雑な規制の全体像が掴みやすくなります。
1.1. ステップ1:建築地の「用途地域」と「指定の有無」を確認する
日影規制は、都市計画法で定められた「用途地域」に応じて適用されます。まずは、建築を計画している土地が、13種類ある用途地域のうちどれに属しているかを確認する必要があります。これは、役所の都市計画課などで確認できるほか、多くの自治体のウェブサイトで公開されている都市計画図でも調べることができます。
そして、その用途地域が、日影規制の対象として「指定されているか」を確認します。住居系の地域はほとんどの場合で指定されていますが、商業地域や工業地域などは、条例で指定されていない限り、日影規制の対象外となります。
1.2. ステップ2:用途地域ごとの「対象建築物」の基準を照合する
建築地が日影規制の対象区域であることが分かったら、次に、計画している建物が「対象建築物」の基準に当てはまるかを確認します。この基準は、主に建物の「高さ」や「階数」で定められており、用途地域ごとに異なります。
例えば、第一種低層住居専用地域では「軒の高さが7mを超える、または地階を除く階数が3以上」の建物が対象となり、第一種中高層住居専用地域では「高さが10mを超える」建物が対象となります。この基準に計画している建物が合致するかどうかを照合します。詳しい基準は次の章で解説します。
1.3. 最終確認:最も重要な地方公共団体の条例をチェックする
建築基準法に定められているのは、あくまで国としての基本的なルールです。どの用途地域を対象とするか、また測定面の高さなどの具体的な運用は、最終的に各都道府県や市町村が「条例」で定めています。
法律の規定をそのまま適用している自治体もあれば、より厳しい基準を設けたり、逆に緩和したりしている場合もあります。したがって、インターネットの情報や一般的な知識だけで判断するのは非常に危険です。計画の際には、必ず建築地の役所の建築指導課などに問い合わせ、その地域独自の条例を正確に確認することが、対象建築物の判定における最も重要な最終ステップとなります。
2. 【用途地域別】対象建築物の具体的な基準を徹底解説
ここでは、用途地域ごとに定められている「日影規制 対象建築物」の具体的な基準について、詳しく見ていきましょう。
2.1. 低層住居専用地域:「軒高7m」または「階数3」がボーダーライン
良好な住環境が求められる「第一種低層住居専用地域」および「第二種低層住居専用地域」では、比較的低い建物でも規制の対象となり、基準が厳しく設定されています。
軒の高さが7mを超える建築物
地階を除く階数が3以上の建築物
この2つの基準のうち、いずれか一方にでも該当すれば、日影規制 対象建築物となります。例えば、平屋や2階建てでも、デザインによっては軒の高さが7mを超えてしまうことがあります。逆に、軒の高さを7m以下に抑えても、3階建てであれば対象となります。この「軒の高さ」と「階数」の2つの側面からチェックする必要があるのが、この地域の特徴です。
2.2. 中高層住居専用地域など:「高さ10m」が基準
「第一種・第二種中高層住居専用地域」、「第一種・第二種住居地域」、「準住居地域」など、中高層の建物が混在する多くの住居系地域では、基準が高さで一本化されています。
高さが10mを超える建築物
これらの地域では、建物の最高高さが10mを超えた時点で、日影規制 対象建築物となります。一般的な木造2階建て住宅の高さは10m未満に収まることが多いですが、3階建てにしたり、屋根の形状を工夫したりすると、10mを超える可能性があります。シンプルな基準ですが、この10mという数字が計画の大きな分岐点となります。
2.3. 商業・工業地域など:条例で指定がある場合のみ「高さ10m」超
「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」では、原則として日影規制の対象区域から除外されています。これは、これらの地域では業務の利便性などが優先され、ある程度の日照の制約はやむを得ないという考え方があるためです。
ただし、地方公共団体が条例によって日影規制の対象区域として指定した場合に限り、以下の基準が適用されます。
高さが10mを超える建築物
したがって、これらの地域で高さ10mを超える建物を計画する場合は、まず自治体の条例で日影規制の指定があるかどうかを確認することが必須です。
2.4. 対象建築物の基準一覧表(まとめ)
これまでの内容を、一覧表にまとめます。計画の際の早見表としてご活用ください。 (※あくまで一般的な基準です。必ず各自治体の条例をご確認ください。)
用途地域 | 日影規制の指定 | 対象建築物の基準 |
第1種・第2種低層住居専用地域 | あり | 軒高7m超 または 階数3以上 |
第1種・第2種中高層住居専用地域 | あり | 高さ10m超 |
第1種・第2種住居地域、準住居地域 | あり | 高さ10m超 |
近隣商業地域、準工業地域 | 条例による | (指定がある場合)高さ10m超 |
商業地域、工業地域、工業専用地域 | 条例による | (指定がある場合)高さ10m超 |
用途地域の指定のない区域 | 条例による | (指定がある場合)軒高7m超/階数3以上 or 高さ10m超 |
3. 高さ・階数の正しい測り方と専門用語
対象建築物かどうかを判断する上で、基準となる「高さ」や「階数」を正しく測ることが不可欠です。ここでは、間違いやすい専門用語と考え方について解説します。
3.1. 「軒の高さ」とはどこを指す?屋根の形状が与える影響
「軒の高さ」とは、建物の外壁や柱の中心線から、屋根を支える部材(垂木など)の最も低い部分までの高さを指します。一般的な切妻屋根や寄棟屋根では、軒先の先端部分の高さと考えると分かりやすいでしょう。
ただし、屋根の形状によっては注意が必要です。例えば、パラペットと呼ばれる、屋上の周囲に設けられた低い壁がある陸屋根の場合、このパラペットの上端までの高さが軒の高さとなります。設計の意図しないところで軒の高さが7mを超えてしまい、日影規制 対象建築物になってしまうケースもあるため、正確な定義の理解が重要です。
3.2. 「地階」の定義と「階数」の数え方のルール
階数を数える際には、「地階(いわゆる地下室)」をどう扱うかがポイントです。「地階」とは、床面が地盤面より下にあり、かつ床面から地盤面までの高さが、その階の天井高の3分の1以上ある階のことです。この条件を満たす「地階」は、日影規制の階数算定からは除外されます。
つまり、地上2階建て+地階1階建ての建物は、日影規制上は「2階建て」として扱われます。このルールを知っていると、敷地を有効に活用した建築計画が可能になる場合があります。ただし、地階のドライエリア(採光のための空堀)の扱いなど、専門的な判断が必要になるため注意が必要です。
3.3. 最も重要な「地盤面」の考え方と高低差のある土地
建物のすべての高さは、「地盤面」を基準(±0)として測ります。土地が平坦であれば問題ありませんが、傾斜地や段差がある土地では、どこを地盤面とするかで建物の高さが大きく変わってしまいます。
このような場合、建築基準法では、建物の周囲の地面の高さの平均を算出した「平均地盤面」を、高さ計算の基準とするよう定めています。この平均地盤面の算定方法は複雑で、専門的な知識が必要です。安易に低い部分を基準に高さを測ってしまうと、実際には対象建築物に該当していた、という事態になりかねません。高低差のある土地での計画は、特に慎重な検討が求められます。
3.4. 意外な落とし穴「工作物」の扱い
日影規制は、建築物だけでなく、広告塔や高架水槽といった「工作物」にも準用される場合があります。これらの工作物も、高さが基準を超え、周辺の日照に大きな影響を与える可能性があるためです。建築物本体の高さはクリアしていても、屋上に設置した大きな看板によって日影規制 対象建築物と見なされるケースもあります。建築物と一体で計画される工作物についても、その高さを念頭に置く必要があります。
4. 日影規制の対象外となるケースとよくある誤解
最後に、日影規制 対象建築物とならないケースや、対象外であることについての注意点を解説します。
4.1. 基準に満たない建築物
最も分かりやすいのは、これまで見てきた高さや階数の基準に満たない対象建築物です。例えば、中高層住居専用地域において、建物の最高の高さを10m以下に設計すれば、日影規制の対象とはなりません。多くの設計者は、規制を回避するために、この基準を意識して高さや階数を計画します。ただし、わずかな設計変更で基準を超えてしまうこともあるため、計画中は常にこのボーダーラインを意識しておくことが大切です。
4.2. 同一敷地内に複数の建築物がある場合の特例
一つの敷地に、母屋と離れのように複数の建物がある場合、原則としてそれらをまとめて一つの対象建築物として日影規制を検討します。しかし、一定の条件を満たせば、それぞれを別の建物として扱うことが認められる特例があります。例えば、2つの建物がエキスパンションジョイント等で構造的に分離されており、用途上も独立していれば、それぞれで対象建築物に該当するかを判断できます。これにより、一方の建物が対象外となり、設計の自由度が増す可能性があります。
4.3. 「対象外=日影を自由に作れる」ではない!日照権との関係
「日影規制 対象建築物でなければ、近隣にどれだけ日影を作っても法的に問題ない」と考えるのは早計です。日影規制は、建築基準法が定める最低限のルールに過ぎません。規制の対象外であっても、隣地の日照を著しく遮り、社会的に許容される限度(受忍限度)を超えるような日影を生じさせた場合、民事上の「日照権侵害」として、損害賠償や工事の差し止めを求められる可能性があります。法律のクリアは当然として、近隣への配慮を欠いた計画は、深刻なトラブルの原因となることを忘れてはなりません。
5. まとめ
今回は、日影規制の中でも特に重要な入り口となる「日影規制 対象建築物」について、その判定基準や注意点を詳しく解説しました。
対象建築物かは、「用途地域」「高さ」「階数」を基準に判断され、最終的には地方の条例で決まります。
低層住居地域では「軒高7m or 階数3」、その他多くの地域では「高さ10m」が重要なボーダーラインです。
「軒の高さ」「階数」「地盤面」といった用語の正しい理解が、正確な判定には不可欠です。
高低差のある土地や、工作物の扱いには特に注意が必要です。
対象外であっても、日照権への配慮は必要であり、近隣とのコミュニケーションが大切です。
自分の建物が対象建築物になるかどうかを正確に見極めることは、その後の設計の方向性を決定づける、極めて重要な作業です。この記事を参考に、まずはご自身の計画の立ち位置を確認し、必要であれば速やかに専門家や行政に相談することをお勧めします。それが、適法でトラブルのない建築計画を実現するための、確実な第一歩となるでしょう。